こんにちは、お茶島です。
今回は、私の母校である横浜国立大学の建築学科で取り組んだ卒業設計について書いていこうと思います。
写真は私の卒制の展示です。2畳くらいの全体模型と奥にメイン建築の部分模型を置いてます。
(模型デカすぎてプレボが小さくみえる笑)
タイトルにもある通り、私は「徹夜ゼロで卒業設計を終える」という、
建築学生からするとちょっと無謀(あるいは甘え?)にも思える目標を立てて挑みました。
理由は単純で、建築を嫌いになりたくなかったからです。
建築の世界って、どうしても「命削ってなんぼ」みたいな空気、あるじゃないですか。
特に卒制は「誰が一番寝てないか選手権」になりがちですし、
朝になっても模型が終わらなくて、カッターを持つ手がプルプルしてる友人たちを何人も見てきました。
もちろん、私もその一人で、何度指を切ったかわかりません。
(これは私のおっちょこが原因でもあるんですが。)
でも私は、「このままじゃ続けられないな」と、ある時ふと思ってしまったんです。
じゃあどうしたら、建築を続けたくなる設計体験にできるのか?
卒制を単なる「課題」ではなく、「これからも向き合っていきたいテーマ」にできるのか?
そんなことを考えながら、私は“徹夜ゼロ”というルールを自分に課して、
建築と、自分自身と、向き合ってみることにしました。
この記事ではその過程を、
悩んだこと・怒られたこと・救われたこと・助けてもらったこととともに、
正直に書いていこうと思います。
これから卒業設計に向かう誰かや、
設計を続けるかどうか迷っているあなたの、何かのヒントになればうれしいです。
↓次の記事たちはこんな感じ
徹夜しない卒業設計を選んだ理由|大学3年の違和感からの決意
大学3年の頃に感じた違和感とは
大学3年の私は、けっこう本気でこう思ってました。
「このまま建築設計を続けることって、本当にできるんだろうか?」って。
横国の教授陣は、世界を股にかけるような建築家たちばかりで、
彼らが普通に講義に来たり、学生の作品を講評してくれる環境って、
今思えばかなり贅沢だったと思います。だからこそ、そんな権威ある人たちに言われる講評はかなりメンタルにくる。
当時の私にとっては、その“贅沢”がプレッシャーの源でした。
「これ、本当に建築でやる意味ある?」
「こんな空間、全然気持ちよさそうじゃないね」
みたいなことを、普通に、さらっと言われます。
ひどいときには
「君、設計向いてないよ」なんて言葉も飛んできます。
(ちなみに、これは当時の彼氏が言われて、めちゃくちゃ落ち込んでました。笑)
たくさんの時間を使って、汗水たらして、
「これ、豊かだな」「綺麗だな」「かっこいいかも」って思いながら作ったものが、
一瞬で一蹴されると、自信なんて簡単になくなる。
「まだ建築はじめて数年の学生なんだから」って頭ではわかってても、当時の私は
やっぱりつらくて、しんどくて、
教授陣のような「建築家」になるためにはそんな業界に居続けなければならなくて、
「果たして私はそれに耐え続けられるだろうか?」って、
真剣に思い悩んでいました。
「心と生活を守る」設計との向き合い方
じゃあ、どうすれば「建築を続けられるかもしれない」って思えるのか?
その答えが、当時の私にとっては——
「ちゃんと寝よう」でした。
鬼シンプル、単純かよ。
でも、本当にそこが出発点だったんです。
でも、これって私にとってはめちゃくちゃ大事なことでした。
ちゃんと寝て、ちゃんと食べて、ちゃんと生活してる状態で設計に向き合うと、
酷評されても、「これだけ自分削ってがんばったのに……」ってならないんです。
いろいろ言われて苦しいことの根本に「自分を削った代償としてこれか」って考えが消えて、純粋に建築に対しての批評になるんです。
批評されても、もっとフラットに受け止められる。
それって、建築にちゃんと向き合うことでもあると思うんです。
もちろん、「削ってでもやれよ」っていう意見もあると思います。
実際、そういうスタンスの建築家が多い世界だし、私も尊敬してます。
でも、それって全員がそうじゃなくていいよね?って思ったんです。
そもそも私はそういうやり方が向いてない。「自分を削ったこと」というバイアスが働いて、建築に対する批評が素直に入らなくなってしまう人間だってわかったんです。
なんでみんな、そんなに目をぎらつかせてやんなきゃいけないのか。
建築学生の“あるべき姿”みたいなものに、自分を無理やり合わせるのって、
やっぱりちょっと違うなと思って。
自分を壊さずに、建築を学ぶ。
そういうスタンスで卒業設計に取り組むって、アリなんじゃないかと思ったんです。
卒業設計とは何か?|建築学生にとっての通過儀礼として
建築学科の卒制が持つ“儀式性”とその背景(横国の場合)
そもそも「卒業設計ってなんなの?」という話から、ちょっとだけ振り返ってみたいと思います。
建築学科では、約4年間の学びの集大成としてこの**卒業設計(卒制)**が存在します。
構造や計画の研究室に進んだ学生は論文で卒業するのに対して、設計を選んだ私たちは、
どんなに途中でイヤになっても、卒制という強敵からは逃れられません。
卒制は多くの建築学生にとって一大イベントであり、
「これを乗り越えなければ一人前じゃない」と言われるような、いわば“通過儀礼”でもあります。
(たまに独学でのし上がっていく人もいるけど、それはけっこうレアケース。)
横国では、およそ1年間をかけて卒業設計に取り組みます。
前期(4年春)には「1万平米」(通称「万平」)という、卒制の前段階にあたる課題が出されます。
これは文字通り「1万平米の影響範囲を持つ建築を設計する」という内容で、
「どこに」「どんな用途の」「どんな建築を」設計してもOKという、超自由課題です。


まさにこんな感じ。自由すぎて、むしろ何やっていいか分からなくなるやつ。マジでムズイ。
この“万平”が終わると、夏休みをはさんで10月から本格的に卒制がスタートします。
(ちなみに横国の夏休みは8〜9月の2ヶ月。最高だったな。)
万平で扱ったテーマや敷地をそのまま卒制に引き継いでもいいし、
すべてをリセットしてまったく新しいテーマで始めてもOK。
私は、テーマはそのままで敷地だけ変えて取り組みました。
卒制に対して、西沢立衛さんはこんなことを言ってました。
「卒業設計って、正直大会なんだからみんなやりたいことに正直にね」
この言葉、終わってから思い返すとまさにその通りだったなと。
「自分のやりたいこと」「大事だと思ってること」「設計で表現したいこと」
それらをどれだけ正直に設計に落とし込めたか。それが結果に出てくる。
西沢さんはこんな言葉も言ってました。
「何かあったときに、それを空間の問題として考えられる人になってほしい」
これ、私の中ではかなり残っている言葉です。
横国で学んだのは、いろんな社会的・文化的・個人的な問題を、
「建築としてどう扱うか」を考える姿勢そのものでした。
そしてそれは今でも、私の中の“建築観”のベースとして根付いています。
卒業設計とは、これまで学んだ建築のすべてを出す場であり、
同時に、これからの人生で「考え続けたいこと」を建築で形にしてみる場でもある。
横国における卒制は、まさにそんな場所だったと思います。
プロジェクト管理力や実務感覚が試される経験
さっきまでは思想っぽい話をしましたが、ここでは技術的・実務的な話。
卒制では、自分の“チーム”をどう運営するかもめちゃくちゃ大事です。
建築学科では定番ですが、4年生は数名の後輩を“ヘルプ”として巻き込み、
図面作成や模型制作をサポートしてもらいます。
(私たちはこのサポートメンバーのことを「ヘルプ」と呼んでました)
自分が後輩だったころは先輩のヘルプについてそのサポートをする。
そして自分が4年になった時には私がヘルプたちに手伝ってもらう。
かつては一緒にヘルプしてた後輩たち(例えば自分が3年の時の2年生)を
チームにひきいれて卒制を乗り切っていく。この流れは連綿と続いていく。
まさにキングダムの麃公将軍の名言「火を絶やすでないぞォ」です。
ヘルプは系譜をともなって、次の世代に受け継がれるのです。
先輩のヘルプに行っていると、ヘルプ同士のつながりができて、いずれ自分のヘルプになってくれることもあります。めんどうかもですが、低学年のうちは先輩のところに顔出すようにしておくとまわりまわって後々楽かもしれません。
私の場合、社会人になった先輩まで手伝いにきてくれました。(陳謝)
このヘルプ運営力=プロジェクトマネジメント力が超重要。
人数が少なければ作業量に限界があるし、
多すぎれば逆に管理が大変になる。
しかも全員が“優秀で丁寧で早い”なんて奇跡的なチームはなかなかないです。
誰に何を、いつ頼むか。
どの段階でどの作業が終わってないと、次の工程に移れないか。
自分の設計が決まってなくても、「とりあえずここ作っといて!」って言える柔軟さ。
…こういうの、全部必要になります。
ちなみに、私の友達のエピソード。
提出直前にヘルプに模型をお願いして「シャワーだけ浴びてくる」と家に帰ったんですが、
なかなか戻ってこなくて、そこからヘルプの後輩たちだけで完成させてたっていう伝説がありました。
(たぶん寝てたんだと思う。)
まあさすがに全部ではないけど、かなーり手伝ってもらってたと思う。
それだけ優秀なヘルプに囲まれたことはある意味本人の力だと思う笑
持つべきものは優秀なヘルプだね。
それくらい、卒制って一人で乗り切るものじゃなくて、チーム戦。
もちろん一人で全部やり切る人もいます。でも、
「人と協力して進める設計」って、社会に出てからすごく活きる力なんですよね。私は今、実務に携わる中で
「今、ボスはこういう状態だから、私はこう動いておこう」という考え方ができるようになったと思う。おそらくこれは、人を動かす側にまわった経験のおかげ。
建築と生活のバランスをとりながら、卒業設計に取り組む——
それは私にとって、建築を「続けたいもの」にするための大事な選択でした。
次回から、「テーマに迷い、どうやって建築にしていくか」という話へ続きます。
卒制ってやっぱり、甘くなかった…でも、楽しかったんです。
↓テーマ悩んだ話に続きます





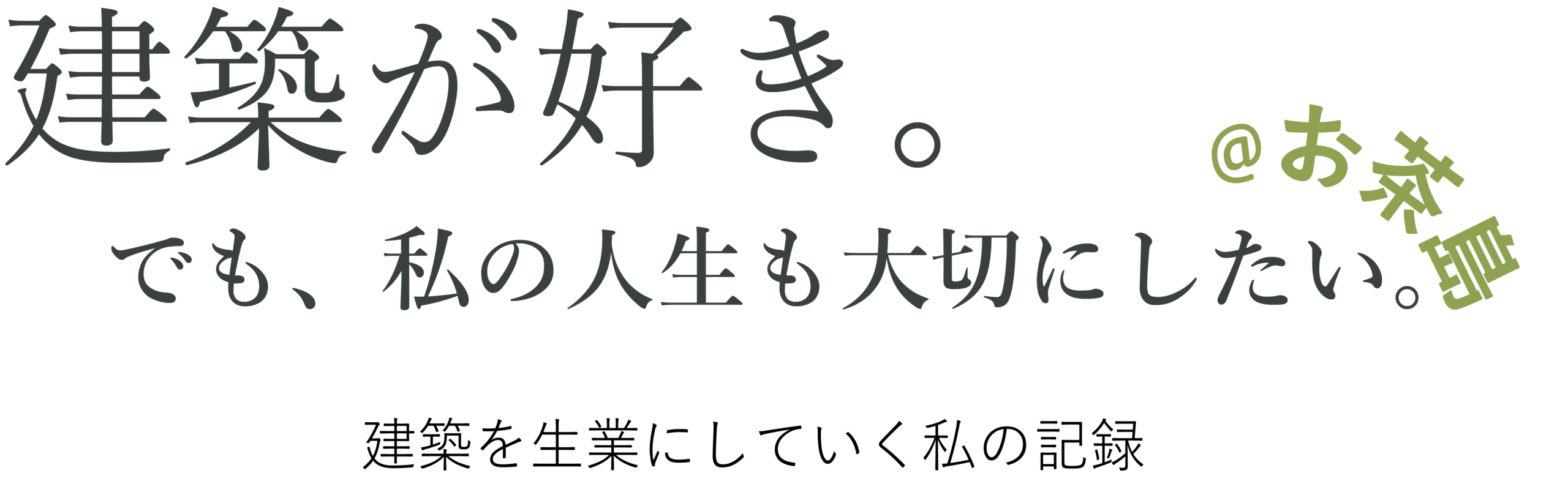






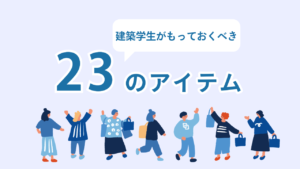

コメント