こんにちは、お茶島です。
豊島美術館ほんとーによかったんですよ。もうほんとに。
だから今回の記事では書ききれませんでした。(スミマセン)
アートスペースに至るまでのアプローチで素敵なことが多すぎて、
本体まで届きませんでした(照)
建築が好きな人なら、きっと一度は写真で見たことがあるはず。
見たことなくても行ったら絶対好きになる。
やわらかくて白い空間に、少しずつ水が湧き出していて、
ただそこにいるだけで、時間も、思考も、ふわっとほどけていくような場所。
写真で見て「すごい」と思っていたものは、
実際に行ってみたら、想像以上に「体で感じるもの」でした。
建築というより、もはや天気とか、空気とか、呼吸に近い。
そんな唯一無二の体験を、
建築が大好きな一人の人間として、できるだけ言葉にして残したいと思いました。
これから訪れる人のヒントになれば嬉しいし、
「行ったことあるよ!」って方には「それな」って共感してもらえたらうれしいです。
行かない人でも行った気になるくらい熱烈に書いていきます。
飛べる目次
アクセス・行き方と現地の雰囲気
豊島ってどこ?どうやって行く?
豊島(てしま)は、瀬戸内海に浮かぶ小さな島。
アートの島として有名な直島や犬島のすぐ近くにあって、同じベネッセアートサイトのひとつとして知られています。
本州からアクセスするには、岡山県の宇野港や、香川県の高松港からフェリーに乗るのが一般的。
私は朝イチ出発の高松港からのルートを選びました。高松駅から港まで歩いて10分くらいなので、アクセスもわりとスムーズです◎
フェリーは30分ほどで到着。
フェリーに乗ってる時間って、なんだか物語の始まりみたいでワクワクしますよね。
別世界に向かっているような感覚になれるのが大好きです。
乗船中も景色が美しくて、すでに美術館っぽい時間が始まってる感すらありました。
以下は豊島美術館の地図です(Googleマップの埋め込み)。広告ではありません。





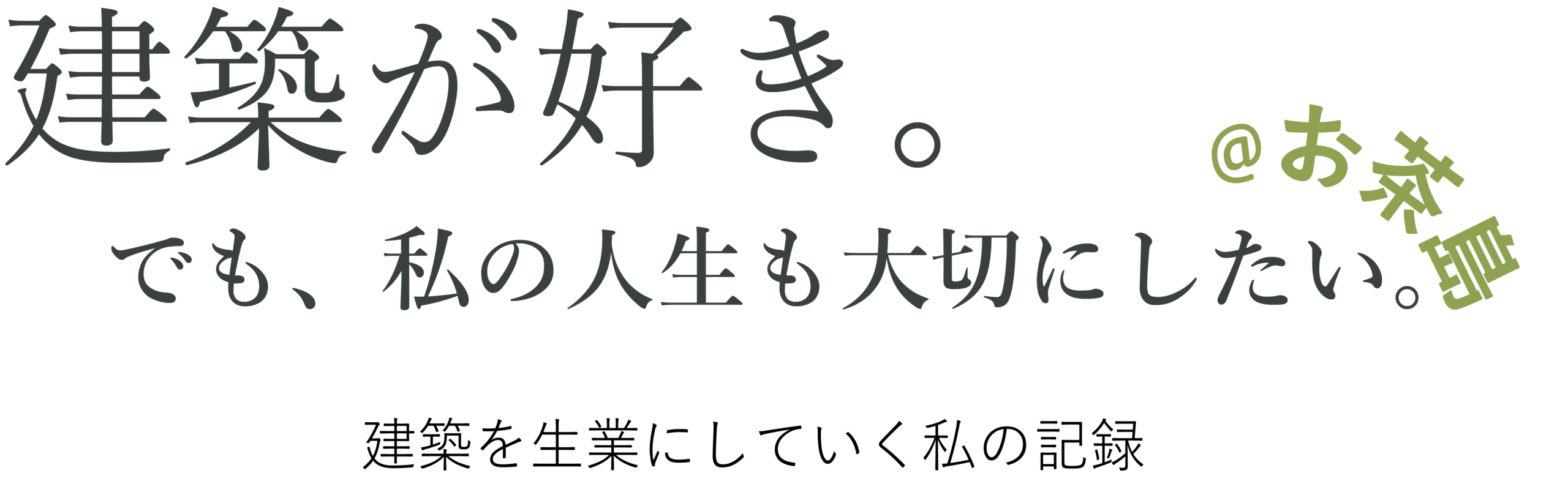


コメント